強迫性障害(強迫症)
強迫性障害(強迫症)とは
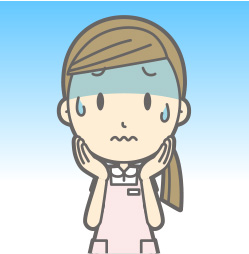
強迫性障害は、強迫観念と強迫行為からなっています。強迫観念は、「少なくとも障害の期間の一時期には、侵入的で無意味あるいは不適切なものとして体験され、無視しようとしたり抑え込もうとしても絶えず心を占める思考、衝動、イメージ」です。強迫行為は、「観念により生じる不安、苦痛を避けたり緩和したり、何か恐ろしい出来事や状況を避けることを目的とし、それがばかばかしいことである、明らかに過剰であると自覚して、止めたいと思いつつも、駆り立てられるように行う繰り返しの行動あるいは心の中の行為です。強迫症状が長期化、慢性化するとうつ病が併発することが少なくありません。
強迫性障害の発症原因
強迫性障害の発症原因として以下の4つが考えられます。環境的な原因
幼少期に受けたトラウマや虐待、厳格な価値観の押し付け、感情や行動を強く否定される体験など、さまざまな環境が強迫性障害のリスク要因となる可能性があります。これらのストレスは単独で影響を与える場合もありますが、複数の要因が複雑に絡み合うことで発症につながるケースもあります。そのため、日常生活の中で経験する小さなストレスや幼少期の心の傷が、強迫性障害の重要な発症要因となり得るのです。遺伝的な原因
強迫性障害は、遺伝が関与しているのではないかとも考えられています。一部の研究では、うつ病やパニック障害に関連する遺伝子が、この障害にも関与している可能性が示されています。ただし、親が強迫性障害を持っている場合でも、必ずしも子どもが発症するとは限らず、遺伝だけでなく他の要因が絡んでいる可能性もあります。生物学的な原因
セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の不足、あるいは脳の視床下部や下垂体の機能異常が、強迫性障害の発症に関係している可能性が示唆されています。こうした身体的な働きに起因する脳の変化が、強迫性障害の要因となることがあると考えられています。外部的な原因
強迫性障害の一部には、連鎖球菌感染症などの感染が関係している可能性が指摘されています。たとえば、上気道炎や化膿性皮膚感染症などが引き金となり、異常な自己免疫反応を起こすことで、強迫症状が早く現れるとする研究結果もあります。ただし、連鎖球菌感染症は多くの場合、体内外に症状を伴わず存在していることが多く、強迫性障害との因果関係については事例が限られており、さらなる研究が求められている段階です。強迫症状の内容
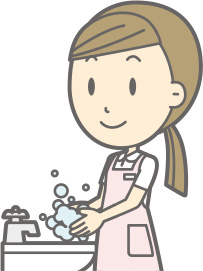
- 汚染恐怖(ばい菌、汚れ、排泄物などに関する心配) 洗浄強迫(頻回の手洗い、入浴、そうじなど)
- 攻撃的な観念(自分の不注意で他人に危害を加える事態を異常に恐れる) 他人に危害を加えていないことを何度も確認する
- 物事の正確性の追求 間違いのないことを何度も確認する 儀式行為
- 数字へのこだわり 何度も数える 不吉な数字を気にする。
- 無用な物へのこだわり 物を収集し捨てずにため込む
- 対称性へのこだわり 儀式行為
強迫症状の具体例(チェック)
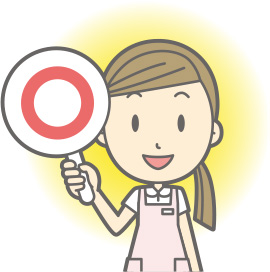
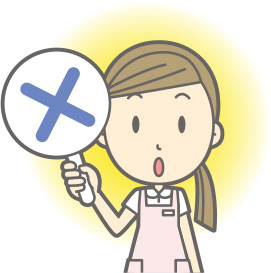
- トイレの後や公共のもの(つり革・ドアなど)に触ったりすると、ばい菌や汚れを過度に心配する
- 汚染されたと感じ、手洗いやシャワーを繰り返す。
- 外出するたびに所持していた物や着ていた服を洗う。
- 自分の排泄物や分泌物に嫌悪感を抱き、過度に恐れる。
- 家を出る時に、玄関の鍵やガス栓、窓が確実に閉まっているかの確認を繰り返す
- 誤字脱字がないか、計算違いがないか、何回も確認する。
- 車の運転の際、人や物をひいたのではないかと不安になり、車を降りて何度も確認する
- 歩いていて人とすれ違った時に、誤って接触してケガをさせていないかを心配して、元の道に引き返して確認する。
- 服を着るなどの日常動作において、特定の順序を守らないと不安になり、間違えると最初からやり直す。
- ものを秩序立てて順番よく並べたり、対称性を保ったり、本人にとってきちんとした位置に収めないと気がすまず、強いこだわりがある。
- 数を数える
- 特定の数字にこだわり、どんな行為もその数字の回数になることを避けようとする
- あるイメージや単語、数字、音楽などが頭の中に浮かんできて、打ち消すことが出来ない。
- 捨てた後でいつかまた必要になるのでないかという恐れから、古新聞・ダイレクトメール・空き缶などの不要な物を何でも貯めこんでしまう