社交不安障害(社交不安症)
社交不安障害(症)とは
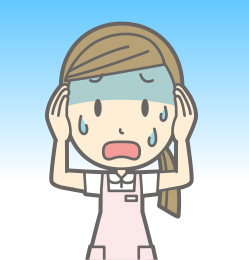
「多くの人の前で話すと緊張する」「初対面の人にあいさつするのは恥ずかしい」などということは誰にでもあることですが、他人から注視を浴びるかもしれない社会的状況や行為に対し、顕著で持続的な不安や恐怖を抱き、そのような状況を回避したり、強い不安や苦痛に耐えなければならず、社会生活や仕事に支障をきたしてしまうこころの病気を社交不安障害(症)といいます。日本での社交不安障害(症)の生涯有病率は1.4%、社交不安障害(症)の人は100万人以上と報告されており、決して珍しい病気ではありません。
発症年齢の平均は13歳で、小学校から中学校の間に発症することが多い。
社交不安障害の原因
社交不安障害の原因については、現時点では解明されていません。 不安や緊張などの感情を生み出す中心的な役割を担っているのが、脳内の「扁桃体」という部位です。この扁桃体の働きには、セロトニンやドーパミンが重要な役割を果たしています。扁桃体が過剰に活性化することで、不安や緊張が強まりやすくなるため、これらの神経伝達物質に関連する異常が原因であると考えられています。ただし、現段階ではその詳細なメカニズムについてはまだ十分に解明されていません。社交不安障害(症)チェック
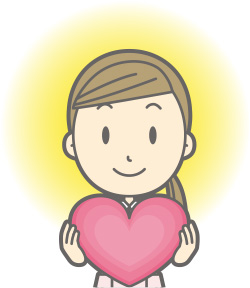
- 人からどう思われているか気になり、人前に出るのを避けたくなる。
- 人前で話したり、自分が注目される場面で強く緊張し不安を感じる。
- 人前で赤くなったり汗をかいたりするので困る
- 周囲の視線が気になり、人混みで動悸や息苦しさを感じる。
- 電話に出ると声が震える
- 人前で電話すると、周囲の人が気になり話すことができない
- 人の見ている前で、文字を書く、作業をすると手が震える。
- 目上の人を怖いと感じ、面談するのを避ける。
- 知らない人のいる集まりに参加することを避ける。
- グループ活動に参加できない。
- 他の人達がいる部屋に入ることが苦手。
- 朝礼やプレゼンテーションで発表する時に頭が真っ白になる。
- 他人と会食することが苦痛である。
- 初対面の人と話すとおどおどしてしまう
- 注意されたり非難されるとどうしてよいのかわからなくなる。
社交不安障害(症)の治療
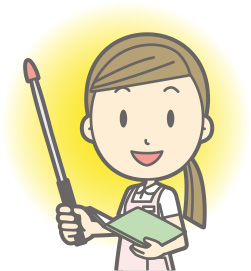
社交不安障害(症)の方は、自分で「これは性格だから仕方ない」と思いこんだり、周囲の人から「気にしすぎだ。意識しすぎだ。気の持ちようだ。」などと言われることがあります。しかし、社交不安障害(症)は、単なる気持ちの問題や性格の問題ではなく治療可能な病気です。社交不安障害(症)は脳の神経伝達物質(特にセロトニン)の機能が低下して不安を感じやすい状態になっているといわれています。また、不安症では、脳の扁桃体の過剰な活動が生じているといわれています。これらに対して、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を服薬するとセロトニンの機能が高まり、扁桃体の過活動が正常化して、不安・恐怖が軽減すると考えられています。
精神(心理)療法としては認知行動療法の有効性が示されています。
うつ病について詳しく知りたい方はこちら
合併しやすい主な病気
社交不安障害が原因となり合併しやすい病気を紹介します。うつ病
うつ病とは、長い時間強いうつ状態が続き、いつもの生活を送ることが困難になる病気です。うつ病は、社交不安障害と一緒に発症することが少なくありません。社交不安障害が引き金となってうつ病を発症する原因として、特定の状況で嫌な体験をした後に自己否定や自責の念を抱くことが挙げられます。たとえば、人前で話すことに対する強い緊張や不安を抱えた状態でスピーチを行い、その後に「緊張して失敗してしまった」「思うようにできなかった。自分は何てダメなんだ」と感じることで、気分が沈んでしまうのです。このような体験が繰り返されることで、次第にうつ病を発症してしまうケースがあります。うつ病について詳しく知りたい方はこちら